【対処&予防編】夜中のギャン泣き。反り返る。何をしても泣き止まない。

夜中にギャン泣きし始めて、何をしても泣き止まない、反り返る。についての原因を
「夜中のギャン泣き。反り返る。何をしても泣き止まない。~原因編~」でお伝えしました。
今回は夜中のギャン泣きで何をしてもダメな時、泣きを長引かせない対処法と予防についてお伝えします。
目次
夜中に泣きだした!抱っこも授乳も嫌がる!どうする?
「夜中のギャン泣き。反り返る。何をしても泣き止まない。~原因編~」で解説しましたが、夜中のギャン泣きの状態の、大前提は「脳は寝ている状態」です。
本人は寝ていたり、周囲の状況が把握できない状態なので、刺激を減らすことが大原則となります。急がば回れと思ってくださいね。
電気・スクリーンはつけない
電気をつけて覚醒させると早く落ち着く気がしますよね。
でも、夜中の光は刺激がとても強く、せっかく体を睡眠の状態にしてくれるメラトニンの分泌を抑えてしまいます。
赤ちゃんだけでなく、対応をしたママパパも寝戻ることに時間がかかったり睡眠の質も落ちてしまいます。

OK:最小限の明るさで赤い光 NG:明るくする/動画を見せる
環境を変えない
寝室は、安全安心な場所です。
心を許して眠っているところで突然の「移動」の刺激は「夜中の緊急事態」のサインになってしまいます。
また、覚醒した時に、自分がいたと思っていた寝室にいないと「ここはどこ?」と混乱したり、
抱き上げる=「起きて移動するよ」の刺激で、「ボク寝たいのに~!!!」とパニックになってしまうことも多く、抱っこしても反り返る状態です。
ところで、不規則な揺れで車やベビーカー、動いていると寝やすくなる「輸送反応」を聞いたことがあるかもしれません。
眠くて泣いている赤ちゃんも、5分歩くと泣き止んで寝たり、落ち着きやすいという研究結果があります。
これは「環境を変える」ではなく「輸送されている時の状態」によるものなので、寝かしつけでもゆらゆらで寝ていた場合は、寝室で静かにそれをしながら落ち着くのを待ちましょう。
夜間のドライブはNG!
夜間のドライブは、大人も寝ている時間になり、大変危険です。
寝不足状態での運転は、普段よりスピードを出しやすく、車線のふらつきが多く、本人も運転について危険を感じていたという研究結果が出ています。
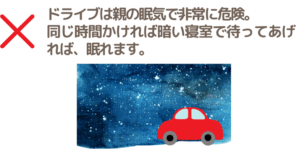
絶対NGは夜中のドライブ
ベストは「優しく一つの方法で時間をかける」
ギャン泣きをしている時は、夢の中で”緊急事態”になっています。
ママパパの急な抱き上げや光など新たな刺激は、その”緊急事態”が起きている時間にも続いている感じに、刺激になってしまいます。
寝始める時はどんな風に寝かせていたでしょうか?
ギャン泣きがスタートしたら、「いつもの寝かしつけ」以外はせず、ママパパも深呼吸をしながら「大丈夫」を伝えましょう。
脳が興奮してしまったら、20分以上、落ち着けないこともよくあることです。
抱っこがダメなら授乳20分→ダメそうならバランスボールで40分…と引き延ばしにならないようにご注意ください。
<あやし方の例>
- 「お休みの言葉をかける」
- 手のひら全体「面」での触れ合い。で背中や胸おでこをゆっくりなでる。
※トントンやバンスなどは「点」での刺激。「面」での刺激より伝わりやすいが、心拍数を下げたり落ち着く刺激は「面」での触れ合いの効果が高い。
[低月齢や夜間時乳の必要がある場合]
前の授乳からしっかり授乳間隔が開いていたら、授乳を受け入れるまで「面」での触れ合いで少し待つ。
[2歳以降の幼児さん]
「それは夢を見たんだね。大丈夫」と普段と変わらない安心な状態と伝えるため、ママパパは体を起こさずに優しく声がけ。
子どもが寄ってきたらそっと撫でてあげましょう。
夜中のギャン泣き予防
寝かしつけや夜泣きの予防はいつも共通。下の2つがとても大切です。
寝る前の疲れ過ぎを防ぐ
お子様に合ったスケジュールで、特に就寝前の疲れ過ぎがないように過ごしましょう。
寝る時間の気持ちの切り替えができないまま寝てしまうと、夜中興奮しやすいです。
また、お昼寝が足りず、お昼寝で処理しきれなかった体験や刺激が夜に持ち越されていると、脳は普段より記憶の整理で大忙し、夢も多くなりやすいです。
寝る前のルーティーンをのんびり
疲れ過ぎないようにすることと同様に、ルーティーンは「これからここでネンネだね」「朝になったらまた遊ぼう」と寝室の環境に慣れたり、気持ちを寝ることに向けるスイッチになります。
夜中、ふと目覚めた時に状況を把握しやすくなりますよ。
夜中のギャン泣き覚醒を慢性化させないために。
「夢を見てギャン泣きは悪い夢を見てかわいそう。」
「悪い夢を見ないように刺激を減らそう。」
と思う方もいるかもしれませんね。
夢を見ることは、とても重要な意味があります。
夢では、日中の体験を再現し、改めて自分にとって重要なことかを確認して記憶を整理します。
また、「万が一こうなったらどうする?」の対処を練習するなど、夢をみることでストレス耐性をつけているという研究もあります。
赤ちゃんは、毎日が新しい刺激。私たちのように「前にもこんなことあったな」がありませんね。
この後自分で生きていくための経験を記憶にしていくために、たくさん夢を見ています。
心配しすぎず、怖がり過ぎず。
あれこれ泣き止ませを行うことで、自分で寝る力や落ち着く力(自己鎮静)を奪わないことも大切にしてくださいね。
夜泣きが慢性化してしまったら
夜泣きや夜の睡眠の不安定さが慢性化してきたら、どんな状態でも改善のステップは3つ!
【慢性化した夜泣きの改善3Step】
1.生活スケジュールと環境を整える
2.栄養、運動を月齢に合わせて楽しく!
3.入眠と親の介入が条件付けられたら(入眠の癖)癖を取るトレーニングを選択肢に。
※トレーニングは生後6ヶ月以降から。2歳前からは乳児期とは全く異なる「幼児用トレーニング」に変わりますので、ご注意ください。
クークールナでは、
- お子様に合った生活リズムで疲れ過ぎずに元気に過ごしたい
- 夜中のギャン泣き、覚醒の原因を教えてほしい。
- 寝かしつけの癖を取って寝ぐずり・夜泣きをなくしたい
- 月齢に沿った、睡眠・栄養・発達のトータルアドバイスが欲しい
など、さまざまお悩みの解決のサポートをしています。お気軽にお声がけください。

- この記事の執筆者
-
子どもの睡眠相談室クークールナ
代表 川口リエ
・GuuMinスーパーバイザー
・クークールナスリープアカデミー講師

